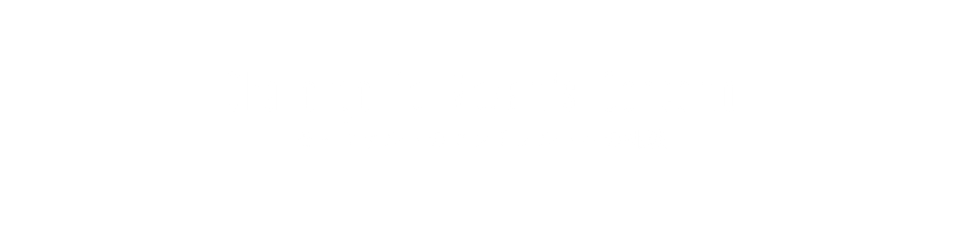かつて機関誌No.184の「先輩こんにちは」にも登場されたピアノ科出身の相澤美智子さん(一橋大学大学院法学研究科准教授)から、興味深いレポートが届きました。ご自身のピアノ科での体験に始まり、現在、ヴァイオリン科で学ぶ娘さんの様子など、モーツァルトのコンチェルトを軸に展開されています。
モーツァルトのコンチェルトへの挑戦
相澤美智子(ピアノ科OG、ヴァイオリン科生徒母)
はじめに モーツァルトのコンチェルトを聴いた最初の記憶は、小学校2年生が終わる3月のことだ。当時、私は8歳。スズキ・メソードに入会して4ヵ月ほどした頃のことで、東海地区のピアノ科卒業式でピアノ・コンチェルト第26番「戴冠式」の第1楽章が演奏された。このときは、オーケストラはなく、ピアノ伴奏で第1楽章のみの演奏だった。「1楽章の演奏だけで15分近くもかかる曲とは凄い」と思ったことだけは覚えているが、それ以外の記憶はない。それから3年後の東海地区ピアノ科卒業式で、私自身が同じ「戴冠式」のソロを演奏させていただくことになろうとは、想像もしなかった。
モーツァルトのコンチェルトを聴いた最初の記憶は、小学校2年生が終わる3月のことだ。当時、私は8歳。スズキ・メソードに入会して4ヵ月ほどした頃のことで、東海地区のピアノ科卒業式でピアノ・コンチェルト第26番「戴冠式」の第1楽章が演奏された。このときは、オーケストラはなく、ピアノ伴奏で第1楽章のみの演奏だった。「1楽章の演奏だけで15分近くもかかる曲とは凄い」と思ったことだけは覚えているが、それ以外の記憶はない。それから3年後の東海地区ピアノ科卒業式で、私自身が同じ「戴冠式」のソロを演奏させていただくことになろうとは、想像もしなかった。
私がモーツァルトのコンチェルトを本気で弾いたのは、卒業式でソロを代表で演奏させていただくために練習をしていたときである。2度目にモーツァルトのコンチェルトを本気で弾いたのは、自身の「戴冠式」から2年後、妹の「戴冠式」の伴奏をしたとき。しかし最近、そのときよりも一段と本気になってモーツァルトのコンチェルトに取り組む機会があった。ヴァイオリンを学ぶ娘の卒業録音のためにコンチェルトの練習をしていたとき、そして、それに続くDuoのパートナーとのコンチェルトの演奏の準備をしていたときである。
④Duoのパートナー・水林彪先生のために、ヴァイオリンコンチェルト第4番の伴奏をする
 左から水林先生、相澤真希子さん、美智子さん 一橋大学に就職して、同じ大学の同僚として出会い、程なくしてDuoのパートナーとなったアマチュア・ヴァイオリニストの水林彪先生と合奏をするようになって、13年。この間に、水林先生は一橋大学を定年退職され、早稲田大学にお移りになり、昨年12月に古稀のお誕生日を迎えられ、今年3月、早稲田大学でも定年を迎えられた。そして5月、先生の古稀のお誕生日と定年退職をお祝いする会が、先生の同僚や教え子たちによって開催された。総勢60名ほど集まったお祝いの会で、先生は皆さんへの感謝の気持ちを込めて、ヴァイオリンの演奏をされることになった。もちろん、それを勧めたのは私である。先生の人生は学問と音楽から成り立っているが、先生が音楽とかかわってこられた時間の長さは、学問とかかわってこられた時間の長さ以上である。ヴァイオリンなしに先生の人生は語れないのであるから、古稀のお誕生日会にヴァイオリンの演奏は必須と思った。また、そのようなお堅いことは抜きにしても、生の演奏があるだけで、パーティーは華やぐ。
左から水林先生、相澤真希子さん、美智子さん 一橋大学に就職して、同じ大学の同僚として出会い、程なくしてDuoのパートナーとなったアマチュア・ヴァイオリニストの水林彪先生と合奏をするようになって、13年。この間に、水林先生は一橋大学を定年退職され、早稲田大学にお移りになり、昨年12月に古稀のお誕生日を迎えられ、今年3月、早稲田大学でも定年を迎えられた。そして5月、先生の古稀のお誕生日と定年退職をお祝いする会が、先生の同僚や教え子たちによって開催された。総勢60名ほど集まったお祝いの会で、先生は皆さんへの感謝の気持ちを込めて、ヴァイオリンの演奏をされることになった。もちろん、それを勧めたのは私である。先生の人生は学問と音楽から成り立っているが、先生が音楽とかかわってこられた時間の長さは、学問とかかわってこられた時間の長さ以上である。ヴァイオリンなしに先生の人生は語れないのであるから、古稀のお誕生日会にヴァイオリンの演奏は必須と思った。また、そのようなお堅いことは抜きにしても、生の演奏があるだけで、パーティーは華やぐ。
お祝いの会にあたり、Duoのパートナーとして私が先生にリクエストしたのは、モーツァルトのコンチェルト第4番の第1楽章の演奏であった。この話をしたのは、ちょうど、娘のためにコンチェルトの伴奏の練習をしていたときであった。正直に言えば、「時間貧乏」の私にとって、娘と水林先生が同じ曲を弾いてくれれば、1曲の練習で2回の本番をこなせるので、ありがたいということはあった。しかし、そのような安直な理由だけで選曲したわけではない。これまで先生と私が取り組んできたのは、ソナタと小品である。ソナタは、ピアノとヴァイオリンが対等な関係になっており、それぞれの楽器の特性や音色の違いを考慮して作られているので、合奏曲として面白いのである。それに対して、コンチェルトは、ピアノがコンチェルトのオーケストラ・パートを弾いても、所詮オーケストラにはかなわないので、貴重な時間を使って、わざわざ」コンチェルトに取り組みたいとは思わなかったのである。
しかし、今回は水林先生が主役の会で演奏をするので、ヴァイオリンとピアノが対等関係にある曲よりも、ヴァイオリンが主役の曲を選曲するのが良いのではないかと思った。モーツァルトの第4番ならばニ長調で、調性的にもお祝いの会に適している。我ながら良い選曲だと思った。先生は、「美智子さんのおっしゃるとおりにいたします」と従順だった。ピアニストにそっぽを向かれては演奏ができないと思われたのか、それとも私の時間のなさに配慮をしてくださったのか。先生も、心のどこかでは、ニ長調のこの曲は会の趣旨に相応しいと納得してくださっていたのだと思いたい。
5月の本番に向けて、水林先生は「ヴァイオリンの先生に、自分のヴァイオリンを見ていただきたい」とおっしゃった。私が仲介し、青木先生のレッスンを受けられることになった。普段、子どもの指導にあたっていらっしゃる青木先生は、水林先生の演奏をお聴きになり、「大人の演奏ね」とおっしゃり、「大学の(法学の)先生にしておくのがもったいない(ほど上手)ね」と評された。私は伴奏者として一緒にレッスンを受けたが、水林先生がレッスンに大いに満足していらっしゃることが、その場にいてはっきりと伝わってきた。青木先生のレッスンというのは、大人の相当上手な演奏者でも満足させるものなのだということを知り、娘がこの先生に師事できることになった幸運に改めて感謝した。
5月の本番に向けて、もうひとかた、ピアニストのレッスンも受けた。私がその方から教わったことで一番心に残ったことは、ピアニスト(ピアノ弾き)としての心構えである。「過去に、本番のピアノが練習のピアノと違い、調子が狂ってしまったことがある」ということを打ち明け、その問題をどう克服すべきかと質問したところ、まず、「このピアノと仲良くしよう、と思ってください」と言われた。そして、「自分の近くで鳴っている音ではなく、遠くで鳴っている音を『聴いて』ください」と言われた。もちろん、自分の音を遠くに立って聴けるわけではないので、あくまでも、自分の音が遠くでどう鳴っているかを考え、想像するだけのことである。しかし、あえて、「それをしてください」と言われた。
5月13日のお昼前、パーティー会場の一橋大学佐野書院のピアノを、私が全幅の信頼を置く調律師に調律していただいた。広い部屋で、調律仕立てのピアノでコンチェルトの伴奏を弾いてみると、不思議なことに、それまで何度も演奏したことがあったけれども、自分が思ったようには鳴ってくれず、「弾きにくい」と感じていた佐野書院のピアノが、その日は、とても弾きやすく感じられた。私の演奏をその場で聴いていらした調律師は、「天井から音が降ってくるようです」と、ピアノの豊かな響きに喜んでいらした。私も、良い本番を迎えられるのではないかという充実した気持ちであった。
ところが、その日の午後、大雨になり、気温が急激に下がり、5月とは思えないような寒さとなった。冬場に演奏をするときには、必ず手袋と携帯用カイロで演奏直前まで手を温める私であるが、さすがに5月にあれほどまで気温が下がるとは思いもせず、手を温める用意がなかった。結局、冷たくなった手を心配しながら演奏を開始せざるを得なかった。冷たい手はカチコチで動かず、音階がスッと勢いよく上がらない、スタッカートが何となくびっこを引く、細かいパッセージで指がもつれる、ということが起きた。心の中で泣き、演奏を途中で止めたいと思ったが、始まってしまったものは仕方がない。この制約の中で一番よい演奏をするしかないと思い直し、心を込めて弾いた。合奏として呼吸が合い、アーティキュレーションが揃い、何より、モーツァルトらしさやニ長調に込められた「天上の喜び」が音で表現されていること。それを一生懸命心がけた。
出来・不出来は、録音をとったわけではないので、良く分からないが、救いとなったのは、自身もヴァイオリンないしピアノを演奏するという音楽通の2人の来客からのコメントであった。1つは、「音楽として魅力的だったので、ミスは気になりませんでした」。もう1つは、「相澤さんの演奏、メッチャ面白かったです。娘さんの伴奏をしているときには、『お母さんの音』になっているんですよ(その方は、娘と私の演奏も聴いたことがある)。でも、今日のは違いました。対等な関係の奏者を思いやっている音でした」
おわりに
考えてみれば、水林先生とも娘とも、バッハやヴィヴァルディのコンチェルトは演奏してきた。しかし、コンチェルトの伴奏をしているという意識は、モーツァルトのコンチェルトの伴奏をしているときと比較して、希薄だった。モーツァルトは、私自身が「戴冠式」でソロ楽器の演奏経験をしているからだろうか、あるいは、バッハのコンチェルトよりも編成の大きい、いわゆるオーケストラの音をレコード・CDで聴いてきたからだろうか。ピアノ伴奏をしながら、頭の中で鳴っている音はオーケストラのそれであり、オーケストラ・パートを弾いているという自覚が常にある。
子ども時代と、大人になってからと、私はモーツァルトのコンチェルトを通して、コンチェルトの世界を――まだまだほんの一歩であるが――教えてもらった。モーツァルトのコンチェルトを本気で弾くという経験は、アマチュア演奏家にとって、そう何度もする経験ではないと思うが、人生のめぐりあわせで、ピアノ科の卒業式で代表で演奏させていただいたり、妹・娘・Duoのパートナーの伴奏をさせていただいたりしたことによって、複数回にわたり、そのような経験をさせていただいてきた。そのたびに多くの学びがあった。そのことを、心から幸せなことだったと思う。
最後に、私の音が、娘と合わせるときには「お母さんの音」になっているということは、以前、細田先生にも指摘されたことがあるが、私は聴くたびに驚いている。まったく無意識だからである。